- ホーム
- セラピストニュース&コラム
- 谷口校長コラム
- 山田桃世さんのセラピストライフ〜施設セラピスト
山田桃世さんのセラピストライフ〜施設セラピスト
2021/12/19
札幌を中心に道内の様々な地域でパーソナルトレーナーとして活動し、また高齢者向けのデイサービス施設でセラピーを提供している、山田桃世さんのセラピストライフを紹介します。
【パーソナルトレーナー】編はこちら
山田さんは、2016年から高齢者向け施設への訪問セラピーを行う「札幌エンジェルハンズ」を主催しています。
「札幌エンジェルハンズ」は、山田さんを中心に、志を同じくする数人のセラピストが、1ヶ月に一度ほど施設に訪問するボランティア活動で、オイルを使ったハンドトリートメントを施設利用者に提供しています。
トリートメントの時間は1人当たり10分ほど。
仲間のセラピストとともに1日に20名ほどの利用者をケアすることもあるとのこと。
何度も訪問するうちに「また来てくれたね」と嬉しそうに声をかけられることもよくあるそうです。
時折、施設職員にもセラピーをすることもあるそうで、施設と訪問セラピストとの関係性の良好さがうかがえます。
こうした活動を始めたきっかけを山田さんに尋ねたところ、「福祉については、昔から興味があったんです」と笑顔で答えてくれました。

同じ想いをもつ仲間たちと
日本女子体育大学を卒業した山田さんは、東京のボディケアサロンに就職し、その後、札幌の自宅でサロンを開業します。
実は、札幌に戻ったタイミングで、介護職に就くことも考えて資格もとったとのこと。
しかし、施設職員や介護士としては、せっかく身に付けたセラピースキルを活かす幅が狭まってしまうのではないかと考えていました。
介護職という選択肢をとらずに、いずれ外部から支援活動をしたいという思いを持ち続けていたそうです。
また一方で、東日本大震災をきっかけにしたボランティア活動も、ずっと続けていたといいます。
被災地にアロマスプレーを送る「アロマ定期便」や、震災の記憶を風化させないための「灯プロジェクト」などをしてきたそうです。
そして、山田さんと福祉ボランティアとの接点は、彼女がセラピストからパーソナルトレーナーへと転身したころに訪れます。
デイサービス施設に勤めている学生時代の後輩から「施設内でセラピーをしてくれないだろうか」との依頼があったのです。
ようやく巡ってきた絶好の機会に、山田さんは二つ返事で応えつつも、継続的に活動をするにはどうすればよいかと考えたそうです。
パーソナルトレーナーの活動と同じく、これも継続性が弱いままに見切り発車してしまえば、施設にも、利用者さんにも不誠実なことになりかねないのです。
「私1人だったらすぐにはゴーサインが出せなかったかもしれません。でも、つながっているセラピストに呼びかけたら応えてくる人たちがいて、それで継続できそうだというところで活動をスタートしました。仲間の存在に背中を押されたように思えます」(山田さん談)
こうして山田さんは数人のセラピストとともに「札幌エンジェルハンズ」として活動をすることになります。
ちなみに「札幌エンジェルハンズ」という名前は、施設職員をしている後輩が名付けてくれたとのこと。
それは、施設サイドに立つ後輩の方から、山田さんに向けた期待と信頼を表しているのかもしれません。
現在は、コロナ禍ということもあって、定期的な訪問は難しいとのことですが、これからも利用者の方たちが何の不安もなく、心地よい時間を過ごせるようなセラピーを提供していきたいと、山田さんは笑顔で話してくれました。
きっと、施設を利用する高齢者たちも、山田さんたちセラピストが来ることを心待ちにしているはずです。
状況が許すようになれば、利用者さんたちの手を、暖かな“天使の手”が包み込んでいくことでしょう。
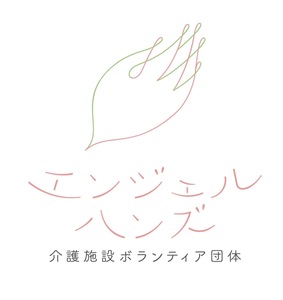
校長からのメッセージ
今後、福祉施設でのセラピーケアは、ますます求められていくものだと思います。
山田さんのように外部からの支援という形もありますし、疲労した施設職員をセラピーで癒やすという形もあるはずです。
医療や介護だけでは対応しきれない部分を、柔らかくカバーする存在として、セラピーは相性がよいだろうと思います。
今後、セラピストライフの一環として、福祉領域に関わっていこうというセラピストも増えていくことでしょう。
さて、こうした活動においても重要になるのが、やはり継続性です。
ボランティアで施設に関わるとしても、セラピストは他に安定した収益がないと、せっかくご縁があっても続かないこともあります。
山田さんは「札幌エンジェルハンズ」のような活動に参加する仲間を増やすためには、参加するセラピストの仕事を助ける仕組みが必要になるだろうと考えているそうです。
たとえば、施設と協力して地域に開かれたイベントを開催し、活動の認知度を高めるとともに、参加するセラピストのことを知ってもらう機会にするというもの。
一般の方とつながれる機会を得ることで、サロンや教室にも来てもらえる人が増えれば、セラピストの収益を助けることになります。
また、施設利用者のご家族に対して提供するセラピーメニューをつくったり、健康教室などを開くことも方法の1つでしょう。
支援を受ける方から直接費用を受け取らずとも、社会活動やボランティア活動が無理なく参加者の収益を助けるような好循環がある。
そのような仕組みは、今後も様々な形が生まれてくるはずです。
私たちは、ボランティアと聞くと、つい「身を削るもの」と考えがちです。
しかし、志の高いボランティアも参加者の生活があってこそのはずです。
積極的にボランティアに参加できるような環境を整えることも、今後の日本社会に求められる考え方でしょう。
社会活動や福祉活動との親和性が高いセラピストだからこそ、ボランティアと収益性を循環させるスタイルを生み出せる可能性を秘めているのかもしれません。
山田桃世










