- ホーム
- セラピストは一生の仕事〜書籍製作ドキュメンタリー
セラピストは一生の仕事〜書籍製作ドキュメンタリー

2016年12月。
セラピスト向けとしては3冊目。私にとって4冊目の新刊
『セラピストは一生の仕事〜心づよいミカタとなるセラピスト・シェルパ30』(BABジャパン)が発売されます。
そこでここでは、【セラピストは一生の仕事〜書籍製作ドキュメンタリー】として本書がどんな想いから生み出されてきたか?を書き綴ってみたいと思います。
セラピストはもちろんのこと、セラピスト・シェルパ(専門支援者)として活動されている方、またはご自身の出版をイメージされている方まで気楽に読んでいただければと。
2016年10月20日 セラピストの学校 谷口晋一
- 「セラピストって一生の仕事になるんですか?」
- 「セラピストになれたら絶対安心ってこと?」
- 「本当の敵は内にあり?」
- 「その存在に気づいていたのはずいぶん前のことでした」
- 「フィールドプレーヤーとシェルパが織りなす業界」
- 「書籍企画書が生まれるまで」
- 「書籍製作チーム〜デザイナー、校閲者」
- 「書籍製作チーム〜影武者シェルパ」
- 「書籍製作ドキュメンタリー〜取材編」
- 「書籍製作ドキュメンタリー〜執筆編」
-
書籍製作ドキュメンタリー〜営業編
- 書籍製作ドキュメンタリー〜著者の責務とは
- 書籍製作ドキュメンタリー〜自分におつかれさん
- 「書籍製作ドキュメンタリー」の最後にあてて。
「セラピストって一生の仕事になるんですか?」

「セラピストって一生の仕事になるんですか?」
目をキラキラさせながら身を乗り出して聞いてくる人もいれば、少し自嘲気味に語る人もいます。
今までどれだけ多くの人から聞いてきた言葉でしょうか。
「そうですねぇ。一生の仕事となる人もいますし、そうでない人もいますよ」
身も蓋もない回答ですが、本当にその通りなんです。
つまり答えがあってないようなもの。
ただ、日本にセラピスト業界が産声をあげて30年以上の月日が流れ。
確実に存在する“セラピストを一生の仕事としている人たち”に僕自身、注目し続けてきました。
彼らからたくさんのことを学び、そのエッセンスをセラピストの学校の教材に活かしたり彼らのメッセンジャーとして発信してきました。
そんな中、2015年のこと。AI(人工知能)が話題になっていました。
ある研究者が10年後生き残る職業、消えてなくなる職業を発表し、
また日本のシンクタンクも日本版のそれとして「人工知能やロボットで代替される可能性が低い100種の職業」を発表しました。
そこには私がセラピストの学校で携わっている人たちの職業名が所狭しと並んでいたのです。(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「セラピストになれたら絶対安心ってこと?」

「人工知能やロボットで代替される可能性が低い100種の職業」には、アロマセラピスト、各種カウンセラー、ネイル・アーチスト、はり師きゅう師などなど。
セラピストの学校で関わったセラピストたちが名乗る肩書が数多く掲載されていました。※
なんだかうれしかったなぁ。
といいますのも、当時「人工知能によって現存の職業がほとんど淘汰される」とセンセーショナルに取り上げられていた中で。
セラピストの学校などで関係するこれだけたくさんの職種が“淘汰されない”と宣言されたのですから。
ただもう一方で、こんな思いが僕の中で浮かんでは消え浮かんでは消え。それが、
「セラピストになれたら絶対安心ってことはない」ということでした。
ちなみに前述の発表の中には、アートディレクターとかクラッシック演奏家なんていうのも挙げられていました。
その肩書ですべての人が生き残ってるかといえば違う。
結局のところ職業としては残る可能性は高いけど、個々で見れば必ず生き残るというわけではない、ということ。
うーん。少し考え込んでしまいました。
『であるなら、続けられる人とそうでない人との違いってなんだろう?』
そういったことを考え発し続ける人間がセラピスト業界の中に一人くらいいてもいい。
でもそのころはまさか本という形になるとは。(つづく)
※野村総研が独立行政法人・労働政策研究・研修機構「職務構造に関する研究」が分類した601種類の職業について定量分析データを使って分析した結果より。
参考サイト:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1512/02/news111.html
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「本当の敵は内にあり?」

セラピストが5年先も10年先も仕事とし、ついには一生セラピストであり続けるためには?
そんなことを頭の片隅に置きながらあるセラピストをサポートしていたときのことです。
そのセラピストはある大きな問題を抱えていました。
話を伺った時には、本人だけの手に負えるものではありませんでしたのでこうアドバイスしました。
「すぐにその分野の専門家に相談したほうがいいと思う。
紹介するから」
結果的にそのアクションが功を奏して解決に導かれるわけですが、そのセラピストのとった行動はいわばレアケースです。
実は多くのセラピストがこんなときに取る行動。それは、
自分でなんとかしようとする。
この抱え込みすぎてしまう性質については出会ってきた多くのセラピストにみられました。
「まずは自分でやれるところまでやってみますね」という言葉を何度聞いてきたことか。。
5年10年という長きにわたり活動をしてきたら、一人で決断や解決できない出来事に直面することは一度や二度ではありません。
人工知能も、景気も、各々の環境もそれなりに影響するだろうけど。結局のところ、
「本当の敵は内にあり」なのかもしれない。
この抱え込みがちなセラピストたちの発想を変えることができたのであれば、
「セラピストって一生の仕事になるんですか?」
この質問に“ひとつの答え”を示せるかもしれない。
今すぐに「一生」と言い切らなくても。
「私はセラピストとして長く続けられます!」
「私はライフワークとしています」と誇りを胸に言い切れるようなセラピストがもっと増えたなら。
そんなセラピストたちに伝え残せるものってなんだ?
それは本書への種が蒔かれた瞬間でもありました。
思えば僕自身がどうしてこの業界に17年もの期間携わってきたのか?
才能あふれる存在だったか?と言えばまったくその逆でして(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「その存在に気づいていたのはずいぶん前のことでした」

思えば僕自身がどうしてこの業界に17年もの期間携わってこれたのか?
才能あふれる存在だったか?と言えばまったくその逆で。
この業界に入ろうと、セラピー技術を学ぶスクールに通っていたときは練習相手も見つからない。
サロンを数店舗出しましたが、スタッフの育成も運営もまるでダメ。
なんでも自分でしようとするので、もう挫折の連続。
たぶん一人で抱え込んだままだったら。1年ももたずにセラピスト業界から撤退し、まったく違う世界に向かっていたと思います。
でもなんだかんだと7店舗まで増やし、そして3年目に必死でつくり上げてきた全店舗を整理売却します。
その後一年に渡って全国の個人セラピストを取材し、当時見渡しても誰もしていなかったセラピスト支援事業を2004年にスタートさせます。
そこから8年の月日が経ちセラピストの学校を設立して、今に至ります。
それまでもうダメだ、と思う時があったか?といえば、それはほぼ毎日。
それを自分一人で乗り切れるわけもなく。
やはり沢山の助けがありました。それも各分野の専門家たちによってです。
その助けてくれた人たちを思い出してみると、まさに多種多様な専門家たちでした。
困ったときや大きな決断をするときは僕の背中にすっと立ち、専門的な知見と視点でサポートし、うまく乗り切れるとあたかも僕が一人で乗り切れたかのように気配を消す。そして知らぬ間に離れて少し遠くで立って見ている。
そんな存在。
ある日のこと、エベレスト登山隊のドキュメンタリー番組を見ていたときにシェルパの存在を知ります。
彼らはあくまでも安全に登山者が山頂に登頂できるようにサポートに徹しています。
あ、僕を支えてくれた彼らってこういった存在だよなぁ。
「セラピストにとって、長く続けていくためにはシェルパの様な存在が必要」
それがセラピストシェルパという言葉が生まれた瞬間でもありました。(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「フィールドプレーヤーとシェルパが織りなす業界」

「セラピストにとって、長く続けていくためにはシェルパの様な存在が必要」
セラピストシェルパという言葉が生まれた瞬間でした。
実は他のプロ業界を見てもそんな関係性が業界を支えていることに気づきます。
各々の業界で活動する存在をフィールドプレーヤーとして。
そのフィールドプレーヤーを支える存在がいる。どの業界においても。
フィールドプレーヤーとシェルパの関係は業界ごとの違いはもちろんありますが、
- シェルパは高い専門性や相手の業界に対する深い知見と経験などからフィールドプレーヤーに最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートに徹する。
- フィールドプレーヤーはシェルパが支える価値を適切に評価し、また複数のシェルパとの接点を持っている。
など。その関係性は共通点があります。
きっとセラピストの業界においてもガムシャラに一人でなんでもできた時代から、
適切なサポートを受けながら集中できる環境に身を置いているセラピスト(フィールドプレーヤー)が活躍できる時代となる。つまりセラピストの業界にとってもシェルパの存在が必要不可欠となる。
と言いますのは、セラピスト業界は第二の揺籃期に移っているからです。
変化することが常態化してかつ、大きな成果が約束されていない揺籃期においては業界内でも動きがどんどん細分化かつ流動化していきます。
ちなみにこのセラピスト業界第二の揺籃期では、他の業界(医療、介護やスポーツ分野など)と協業となったり、小さな団体が規模拡大という目的だけでなく価値ある活動を継続しようとしたりする。と僕は考えています。
そんな時代がしばらく続くとするならば。今までの成功事例を真似てもやはりそれだけでは通用しない。
つまりセラピストがしなやかに5年、10年。そして一生に渡って活動を続けていくためには、
いかにして「自らの中でのウィークポイントは何か?」「セラピーに集中できる環境を生み出すための障壁は?」を把握してそれをどう補足、解決していくか?を見極めていく必要が出てくると考えたのです。
やはりそれぞれの状況に合わせたセラピスト・シェルパを見出せるセラピストこそが“ロングライフセラピスト”となる。
そのころからこのことをテーマとした出版企画書の枠組みが固まりつつありました。(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍企画書が生まれるまで」

セラピストはもっと甘え上手になって、自分の不得手なものを専門家に委ねる。
そんな想いを持つようになった僕はそれをどう発したらいいのだろう?と考えていました。
セラピストの学校の教材としてやオープンスクールなどでコンテンツとすることも考えましたが、それだと手に届く人が限られます。
そこで書籍にできないか?と考えたのです。
◇◇◇ ◆◆◆ ◇◇◇ ◆◆◆ ◇◇◇ ◆◆◆
最初に自分なりの企画書を作ります。
実はこれは企画書という名の自己満足資料に過ぎませんので、それを手にいろんな人に相談してみます。
必ずしも書籍になるとは限りませんので「こんな風に感じているんだけどどう思う?」くらいな、緩い雑談ですが。
でもこの緩い雑談こそが僕にとっては書籍企画につながるポイントなのです。
将来書籍となり、書店に並び手に取った人が表紙を見てどんな反応を示すか?パラパラとめくったときにどんなページに目を留めるのか?などをイメージしながら書籍企画書として作り上げていきます。
そしていよいよ出版社に企画書として持ち込むこととなります。
出版社とのご縁はいくつかありましたが、今回は「オンリーワンのセラピストになる!」「セラピストの手帖」などでお世話になったBABジャパンさんにまずは相談しようと。
何回かの打ち合わせののちにゴーサイン(執筆開始)が出ました。
ただ、採用された書籍企画書がそのまま本になるとは限りません。
大きな枠組みは変わりませんが、内容は時々で変化するものです。
そこで大切なのは編集担当者との信頼関係です。
名古屋を出発し新宿駅のレトロな雰囲気の喫茶店で何度となく打ち合わせました。
これから著者と編集担当者でいわば共同作業を行っていくわけですから、彼の中の本づくりにかける思い、プロフェッショナリズムのようなものを知りたくて色んな話を聴きました。
そして、次にこの企画に関し僕が思いの丈をぶつけます。
すると「なるほど。つまりこういうことですね」と瞬時に要約して言葉にしてくれるわけです。
これは編集担当者(僕にとってのシェルパ)の専門技術の一つだと感じました。
「そんな表現方法もありだよな」とそれを僕はノートに書き留める。
テーブルが小さいのでノートがコップに当たって落ちない様にしながら。そんなことの繰り返し。
こうして書籍の枠組みの精度が高まってきた段階で次に移ったのは、原稿執筆ではありませんでした(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍製作チーム〜デザイナー、校閲者」
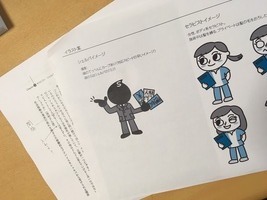
こうして書籍の枠組みの精度が高まってきた段階の次は原稿執筆ではなく、あることでした。
それは「書籍製作チームの結成」です。
書籍が作られていく最初のプロセスでは編集担当者との関係性が一番大切です。
と同時に日々同時進行で様々なことをしている身として。
書籍を作り上げていくには陰で支える(僕にとっての)シェルパの存在が不可欠です。
と言いますのも、僕の雑な性格からして気づかぬうちにクオリティが低いまま執筆活動その他を進めてしまう可能性があるからです。
(ですので著者が全員製作チームを必要とするか?といえばそうとはいえません)
最初に向かった先は北海道。イラストデザイナーとなるシェルパに相談するためにでした。
飛行機に乗りまだ雪の残る北海道に。
本を一つの作品として考えますと、読者がパッと手に取った時やパラパラとめくった時の受け止める印象がとても重要です。
つまり本文の内容もさることながら、おざなりにできないのはタイトルと装丁(表紙デザイン)、そして本文にあるデザイン、イラストたちです。
著者の想いを汲み取り、著者もちょっとしたニュアンスの違いを伝えやすく、当然のことながらデザイン力に優れるシェルパ。
だからこそ。僕はどうしても彼らに関わって欲しかった。
そして、もう一人のシェルパとして声をかけたのが校閲者です。
(これも僕自身の能力によるのですが)誤字脱字など僕一人で防ぐことは無理です。
最終的には出版社が責任を持って最後対応してくれますが原稿を提出する段階であったり、また最終段階においてチェックしてもらうシェルパが必要でした。
実は前作まではこのシェルパはチームメンバーにはいませんでしたが、原稿執筆段階であまりに僕の文章には欠けがありましたから本書から加わってもらいました。
そして最後に。著者の精神的支柱となるシェルパです(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍製作チーム〜影武者シェルパ」

そして最後に。チームにとってなくてはならないシェルパの存在。
いわば僕の影武者と言いましょうか。
原稿執筆をつづけていますと。どうしてもアイデアや執筆そのものに詰まってしまいます。
また調子よく執筆できていたとしても、編集担当者からの指摘で独りよがりの文体になっていることに気づかされるときもあります。
そんなときにこのシェルパは、全体の構成を元に僕の文章のクセをとらえながら軌道修正してくれたり、ボタンのかけズレを様々な段階で気づかせてくれるシェルパです。
時にふと尋ねられる存在でもあり。
気分転換にご飯を食べにいったり、具体的に相談もできる。
僕の考えていることをバーっと広げてくれたり、整理してくれたり。
ですので精神的支柱としてのシェルパといえます。
◇◇◇ ◆◆◆ ◇◇◇ ◆◆◆ ◇◇◇ ◆◆◆
このように著者をサポートしてくれるシェルパに何人も支えられてこの本は出来上がってます。
当然のことながら出版社も、頼りない僕を支えるための役割を負っている方が何人もいるはずです。
どうしてこれだけの人が関わってくれるか?といえば。
すべては、
「本書を手に取ってくれたセラピストのみなさんやセラピスト・シェルパを目指す方たちのために。」なのです。
さぁ頑張って執筆しよう!と思いたいところでしたが。
まだ執筆にはとりかかれません(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍製作ドキュメンタリー〜取材編」
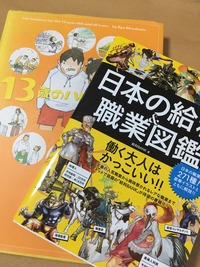
さぁ頑張って執筆しよう!と思いたいところでしたが。すぐには執筆できない事由がありました。
本書の中心テーマであるセラピスト・シェルパの情報が本とするにはまだまだ少なかったのです。
この時点で決まっている構成として、
- セラピストはそれを一生の仕事にできるのか?という大きな問いかけからスタートし、
- 時代背景や業界の流れなどを把握する中で10年というスパンでの活動ポイントを伝え、
- セラピストを専門的に支援する存在(セラピスト・シェルパ)の紹介と、
- セラピスト・シェルパの活用事例や問題点などを提示し活用していくことを提案する
という骨組みだけが固まっていました。
しかし。
その柱の中心であるセラピスト・シェルパの情報があまりにも漠然としています。
セラピスト・シェルパという言葉はふと浮かんできた造語ですから、インターネットで得られる情報はドンピシャなものはありません(当然といえば当然ですが)
つまり情報収集や整理を同時並行でしなくてはいけなかったのです。
セラピストの学校で全国各地のセラピストたちと出会ったときには実際にそんな存在はいないか?と尋ねてみたり。
ヒントになるかも?と、世の中に出ている職業図鑑などを入手してみたり。
今回は30種のセラピスト・シェルパに登場していただいていますが、候補に挙がったのは約50種のシェルパたち。
実際の事例や、マッチングの可能性を想像しながら泣く泣く30種に絞り、そこから取材です。
でもしかし、これがなかなか大変で。
直接お会いしてのインタビューやスカイプや電話でのインタビューなど。
接点の持てなかったシェルパについては、事例提供をしてくださったセラピストにインタビューをするなど。
一応ICレコーダーなども用意しましたが、記者ではありませんのでほとんど使いませんでした。
実際はインタビュー中のメモ書きと、自分の中で生み出されたセラピストとセラピスト・シェルパとの関係性を整理したものとなりました。
そうしてやっと執筆活動が本格化するようになりました。
ちなみに執筆について知人からは「あっちいったりこっちいったりしているのに、よく執筆できますね?」とたずねられます。
実は僕は事務所で執筆はほとんどしません。と言いますのも(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍製作ドキュメンタリー〜執筆編」

そうしてやっと執筆活動が本格化するようになったのですが、僕は事務所や自宅など一つ場所で執筆はしていません。
と言いますのも、キーボードでのタイピングがそんなに得意ではないからです。
ブラインドタッチでサラサラと入力できればいいのでしょうけど、頭の中に浮かんだ文章をタイピングしていくスピードが追い付けません。
しばらく打ち込んで画面をみたら、おおよそ日本語でない文章の羅列が。。
ということもあり今現在の僕の執筆スタイルはこうです。
- 頭の中の骨組みを元に書きなぐるようにメモ書きする
- そのメモ書きを反芻しながら一つの文章にする(これも手書き)
- iphoneの音声入力機能で手書きされた文章を読み上げ、入力された原稿を元にフリック操作で誤入力を修正する
- プリントアウトして赤ペンで添削する
- wordなどにまとめて改行や句読点をチェックする
- 再度プリントアウトして赤ペンで添削する
- シェルパの力も借りて原稿化する
この執筆スタイルですと、ほとんど事務所や自宅でする必要はありません。
執筆活動の場所は主に移動中と…全国にあるスタバでしょうか?
こうして執筆が進んでいきます。
もちろんその間に、編集担当者に出来上がった原稿を送ってアドバイスを受けて追加執筆したり、チームシェルパと連絡を取り合って進行状況の確認をしたり。
後半は著者原稿からデザインや校閲への展開も進めていきました。
おぼろげな構想から計算すると約半年が過ぎるころです。
たった一人で書籍製作はできない、という感覚を持てたのは彼らのおかげです。
そして原稿がほぼ出来上がった段階で、著者が次にしなくてはいけないことがあります(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
書籍製作ドキュメンタリー〜営業編
そして原稿がほぼ出来上がった段階で著者である僕が次にすることがありました。それは、
この書籍をどのようにして販売していくか?という営業戦略への関わりです。
「なにもそこまでしなくても。」と思われるかもしれません。
(実際に著者の中にはまったくノータッチという方もいます)
しかし。僕は可能な限り関わらせてもらえるよう出版社にお願いします。
心血注いで作り上げた書籍ですから、純粋に一人でも多くの人に知ってもらいたいですし手に取ってもらいたいわけです。
ただこれは出版社の意向をしっかり受け止めなければなりません。
最初の書籍(福業のススメ)でお世話になった出版社さんの時は、全国の書店を回りました。
その数60店舗。それがきっかけで朝の情報番組に出演したり、一日密着取材なんてのも経験しました。
そして今回お世話になるBABジャパンさんも特徴的な営業戦略を持っていますから、そこで著者としてやれるべきことはなにか?を打ち合わせます。
いわば著者という演者の役目を果たすのです。
この経験はセラピストの学校の校長という立場としても大いに活かされます。
ブランド学科の修了生やマンツーマンサポートをした生徒さんの中には書籍を出される方が少なからずいます。
そんなセラピストに対して営業戦略のアドバイスにつなげることができますし、「原稿を書きさえすれば後は何もしなくていい」「打ち上げ花火をとにかく大きくすれば自然と売れる」という偏った著者観を軌道修正することができるからです。
出版社の営業担当者などと打ち合わせも終えて。
もうこのテーマにかかわって10ヶ月ほどと、ずいぶん時間が経過しました。
まだ書籍のカタチにすらなっていませんが、戦いはこれからです(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
書籍製作ドキュメンタリー〜著者の責務とは
発売から約4.50日前となりますと、まさに一日一日が発刊に向けてのラストスパートとなります。
今まで出した原稿と、デザイナーから来たイラストデザイン、紙質や色刷りパターン、誤植修正や言い回しの共通化など、それぞれの編集担当者をはじめとするシェルパによって一冊の形となっていきます。
当然著者である私も送られてきたデータを見て、原稿執筆した時にはいいと思ったけど実際文字となると内容を微調整する必要が出てくるのもこの時期です。
ちなみにこの時点で大切なことは、全体のバランスが崩れない様に前後の文脈を押さえつつ、文字数も極力合わせて差し替えるための追加原稿を書いていきます。
ですのでもうなんども原稿を見返す中で、お腹イッパイ。。となるのがこの時期です。
で、いよいよ著者の手を離れる脱稿のとき。
その瞬間は最後の最後まで躊躇します。
「これで世の中に出る。さぁすべてを受け止める覚悟をもつんだ」と。
いくらプロフェッショナルな編集担当者がいたとしても。
チームシェルパにしっかり関わってもらっていても。
一旦著者名として自分の名前が載ったら。
どんな指摘や評価も自分に対して。となります。
それが著者の責務でもあるわけです。
さて。前書もそうだったのですが、僕はいつもこの時点で「自分にお疲れさん」をします(つづく)
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
書籍製作ドキュメンタリー〜自分におつかれさん

原稿が著者である自分の手元から離れたこの時点で、いつも僕は「自分におつかれさん」をします。
人によっては長期一人旅とか、色々あるようですが。
僕の場合は腕時計を買う、というものです。
といいましても高級時計の部類ではなく無名のアンティーク時計やメジャーでない機械式時計とか。(執筆中は時々アンティークショップや時計店に足を運んで眺めてました)
新書を出すために集中してきた時間は目に見えませんが、腕時計という形で目に見える形にして後々一人勝手に喜ぶという。また、その時計を身につけるとそのときのしんどさや達成感を味わえます。(すべて“こじつけ”ですが)
ただ書籍が発売されてからも、営業活動含め著者の働きは続きます。
残念ながら著者というだけで未だにチヤホヤされる事もあり、そこに対して自戒し続けるためにも。
この瞬間だけは、自分におつかれさん。なのです。
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |
「書籍製作ドキュメンタリー」の最後にあてて。
この「書籍製作ドキュメンタリー」も最後となります。
本書のタイトルである、「セラピストは一生の仕事〜心づよいミカタとなる、セラピスト・シェルパ30」にかける僕の想いとは。
多くのセラピストに会ってきて、常に願う想いでもありました。
セラピストとしてせっかくこの世界に入ったのですから、一生と言わずとも。
1秒でも長く。そして1人でも多くのクライエントと対峙して欲しい。
やはりそのためには覚悟が必要です。
世の中にはセラピストを必要とする人が沢山います。
あなたをずっと探し続けています。
そのためにあなたができることがあり、
できることというのは「人に委ねる」ということも含まれているのです。
本書を通してそのことに気づいたり、行動してもらえたのであればそんなに嬉しいことはありません。
2016年11月 セラピストの学校 谷口晋一
|
谷口校長新刊紹介&製作秘話はこちら ≫ 詳しく 直筆メッセージ入り書籍のお申込はこちら ≫ お申込み amazon注文ページはこちら ≫ amazonで注文する |










